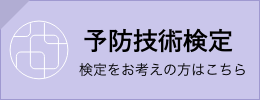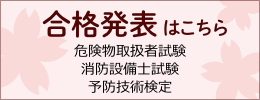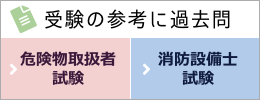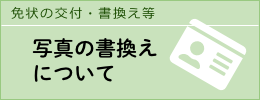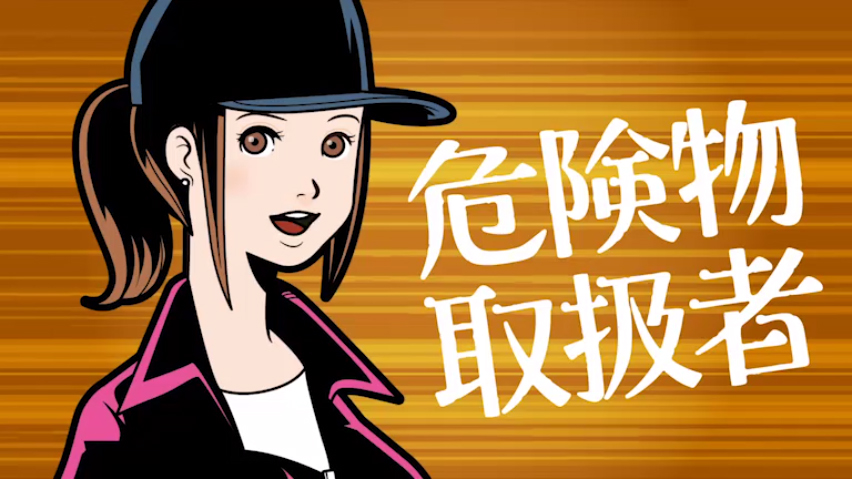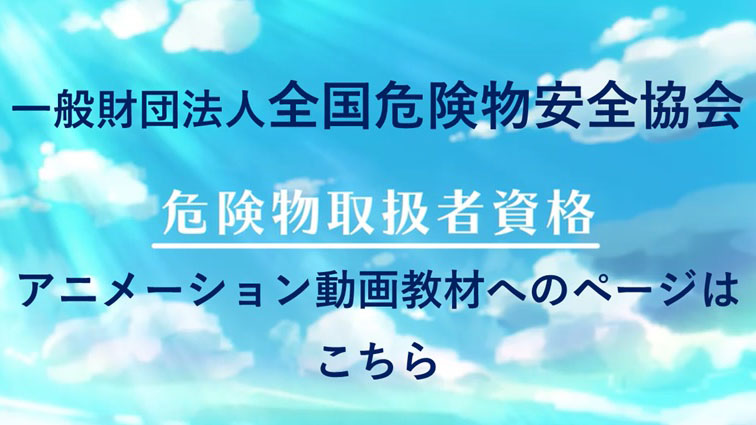よくある質問
- Q1予防技術検定とはどのような試験ですか。
消防庁告示の規定により、消防本部及び消防署等の機関には、建築物の大規模化・複雑化等に伴い高度化・専門化する予防業務を的確に行うため、火災の予防に関する高度な知識及び技術を有する「予防技術資格者」を配置することとされています。 「予防技術資格者」になるためには、予防技術検定に合格する必要があります。 詳細はこちらをご確認ください。
- Q2予防技術検定の受検資格はどのようなものか。
予防技術検定の受検資格は4種類あり、「消防庁告示に定める講習(消防学校において行われる講習等)の課程を修了した方」「大学、高等専門学校、大学院において理工系又は法学系の学科又は課程を修めて卒業した方」「大学、高等専門学校、大学院において、機械・電気・工業化学・土木・建築又は法律に関する単位を通算して20単位以上修得した方」「消防署での予防業務に1年以上の従事経験がある方」となっています。詳細はこちらをご確認ください。
- Q3検定日を知りたい。また、毎年度の検定日はいつ頃になれば分かりますか。
検定日は例年7月上旬に当センターのホームページに掲示します。詳細はこちらをご確認ください。
- Q4受付期間は、いつからですか。
受付開始日の9時00分から締切日の23時59分までです。
24時間対応ですが、毎週土曜日午前3時から5時まではメンテナンスの為申請不可です。余裕をもって申請してください。詳細はこちらをご確認ください。- Q5居住地以外の都道府県でも受検はできますか。できるとすれば、どのような手続きが必要ですか。
電子申請の受検地選択画面で、ご希望の受検地の都道府県を選択していただければ、どちらの受検地でも受検することができます。
- Q6受検手数料はいくらですか。
令和7年度から6,600円になりました。
- Q7予防技術検定の受検願書は、郵送で送ってもらえますか。
書面による願書申請は廃止になり、原則オンラインによる電子申請になりました。
詳細はこちらをご確認ください。- Q8昨年度の受検願書の用紙を使用してもよいでしょうか。
使用できません。
令和7年度から、予防技術検定を全面電子申請化しました。申請受付期間になりましたら、こちらから電子申請をお願いいたします。- Q9複数人でまとめて申請及び受検料の支払いができますか。
団体で申請をし、支払いを一括で行う「団体一括申請」という方法で消防本部単位でまとめて受検申請ができます。詳細はこちらからをご確認ください。
- Q10過去に受検したことがある場合、受検申請時に前回提出した書類で代替できるものはありますか。
過去に受検したときのフリガナ、氏名、受検日、受検番号、資格コードを入力することで、過去と同内容の証明書類は省略できます。
- Q11予防技術検定の検定時間(開始から終了まで)はどのようになっていますか。また、途中退室は可能ですか。
検定科目の一部免除が無い場合の検定時間は、予防技術検定の場合、2時間30分になります。 途中退室は、検定監督員の指示により可能となります。
- Q12過去に合格した区分と同じ区分を受検できますか。
可能です。
- Q13同日に危険物取扱者や消防設備士の試験を受験することはできますか。
できません。
- Q14貴センター発行の問題集や参考書を購入したいのですが、どこで購入できますか。
当センターは検定実施機関として、公平・公正な検定を実施するため、学習方法や参考図書の案内及び参考書、問題集の出版、販売並びに検定準備講習等は行っていません。
- Q15参考書を購入して勉強しましたが、参考書どおりに検定問題が出題されませんでしたがどうしてですか。
当センターは、検定実施機関として公平・公正な検定を実施するため、参考書の作成・販売には一切関与しておりません。 従いまして、参考書の内容につきましては、出版している会社に直接お問い合わせくださいますようお願いいたします。
- Q16法令改正がされた場合、予防技術検定の問題は新しい法令で出題されるのですか。
予防技術検定の問題は、実施する年度の4月1日を基準とし、施行されている法令等に基づいて出題されます。 例)令和7年度の予防技術検定は、令和7年4月1日において施行されている法令に基づき出題。
- Q17検定問題で分からないことがあったので、教えてほしい。
当センターは、受検者が予防技術資格者としての知識を有しているかどうかを判断する検定の実施機関であり、公平・公正な検定を実施するため、検定問題の内容については一切お答えしていませんので、ご了承ください。
- Q18複数の検定区分を同時に受検したいのですが可能ですか。
同時に複数の検定区分を受検することはできません。
- Q19防火査察の区分に合格しています。防火査察の区分以外を受検する際には、検定科目の免除措置はありますか。また、その場合の検定時間はどうなりますか。
既に予防技術検定を一つの区分でも合格している方が他の区分を受検する場合は、検定科目のうち「共通科目」を免除することができ、「専攻科目」のみの受検となります。この場合、解答問題数は20問で検定時間は100分です。 受検の際、検定科目の免除を希望される場合は、電子申請の願書情報入力画面で「科目免除あり」を選択してください。
- Q20「共通科目」の免除を受けた場合の合格基準はどのようになっていますか。
「専攻科目」のみを採点し、正解率が60%以上で合格となります。
- Q21合格発表の方法を知りたいです。
合格発表は、ホームページ上に公示します。また、受検された方全員に結果通知書を公示日に発送します。
- Q22合格証明書を紛失したので再発行できるか。
予防技術資格者の認定のときのみ再発行可能です。
- Q23団体申請の流れを教えてください。
① 団体情報の登録
② 団体の申請
③ 受検手数料の支払い(コンビニ払い又はペイジー払いのみ)
④ 支払い完了
⑤ 受検票のダウンロード(受検日の10日前から可能)
⑥ 受検当日
⑦ 領収書・合算書のダウンロード
⑧ 合格発表
⑨ 検定結果通知書の受け取り(当センターから受検者本人へ郵送)
- Q24団体申請で払込手数料はかかりますか?
団体申請では、払込手数料はかかりません。(センターで負担します。)
お支払いいただく金額は、6,600円×受検人数 です。
- Q25公費受検と自費受検の者がいるのですが、団体申請を2回に分けて実施することはできますか?
団体申請を2回に分けて行うことはできません。
上記の場合、公費受検を団体申請、自費受検を個人申請とする方法があります。
- Q26団体申請は、1名でも可能ですか?
団体申請は、複数名が受検する際、申請できます。
1名の場合は、個人申請をしてください。
- Q27団体申請をしてコンビニ等で受検手数料を支払う際、期限はありますか?
仮受付完了日の翌日から3日以内です。
※ 仮受付とは・・検定手数料の支払いが完了していない状態
- Q28支払期限が切れてしまいました。
申請が完了していませんので、再度申請し直してください。
電子申請の受付期間内であれば、再度、最初から電子申請をやり直し、払込みを行うことにより受検が可能です。
- Q29領収書を発行して欲しいです。
領収書は、検定日の翌日から発行可能となります。
団体の代表者様が、ホームページ上からダウンロードしてください。
なお、団体申請は消防本部宛の「合算書」、個人宛の「領収書」がそれぞれ発行されます。
- Q30請求書を発行して欲しいです。
請求書の発行は行っていません。
- Q31支払い期限を延ばしてほしいです。
延長はできません。願書情報入力で「一時保存」画面がありますので、活用してください。
支払期限が切れた場合、再度新規で登録してください。
- Q32領収書や合算書の宛名を変更したいです。
宛名の変更はできません。
- Q33団体コード・団体確認キー・団体代表者キーは、来年度以降も使用できますか?
来年度以降も同じコードをお使いいただきます。大切に保管してください。